モスクワ大公国プレイ 1494年~1535年
タタールの軛からの脱却 1494年~
スウェーデンを属国とし、イヴァン3世が死去しヴァーシリー3世(3/2/3。前回で2/3/5と記載したがミス)が即位した1494年から再開する。デンマーク戦後は北欧の供給限界が低いこともありこちらの人的資源も払底してたため、しばらく休息する必要があった。その為戦後10年は衰弱したカザンを併合した以外は軍事行動を起こさず回復に努めていたが、1505年に今度はノルウェーの属国委譲を目的として第二次デンマーク戦を開始した。属国の委譲ボーナスは大航海時代が終わってしまうとなくなってしまい、開発度の関係でノルウェーを委譲させることができなくなってしまう。大航海時代は大体1510年くらいに終わる為、この時期に仕掛ける必要があるのだ。

ノルウェーを属国として獲得した後はいよいよ大オルダへの拡大を目標とする。モスクワはミッションで大オルダの領土に広大な請求権を貰えるが、大オルダはティムールと同盟を組んでおり正面からでは軍量的に厳しい。そこで今回は大オルダと同盟を組んでいるウズベクに宣戦する方法を使って対峙する。大オルダ和睦の際は領土は1領しかとらず、外交関係の破壊や賠償金の取得をメインとした。前回も記載したが領土管理限界がカツカツであるためである。また、このタイミングで賠償金を元手に施設を建てて収入を改善することは、豊富な軍量を支える経済力に乏しいロシアに今後に生きてくる。

大オルダ戦のあと、孤立した大オルダからクリミアが領土を獲得して領地を接した為これに宣戦する。クリミアには有力な同盟国がいない為快勝できるが、注意点として和睦の際はクリミア方面はとってはいけない。ポーランド・リトアニア戦を見据えてオスマンと同盟することを目指しているが、クリミアにはオスマンの強烈な領土欲がついているため獲得すると同盟できなくなってしまう。拡張に制限があるのはもどかしいが、こうした拡大の駆け引きもEU4の醍醐味の一つだ。

大オルダ戦の後、事前に行っていたオスマンとの関係改善が功を奏して同盟を結ぶことが出来た。信頼度を80以上にすることでライバル指定されることがなくなるので、忘れずにおべっかを使ってゴマすりしておこう。
オスマンと同盟出来ればAEを気にする必要はなくなるし、この頃には拡大によって遊牧民国家との軍量差も歴然となっているはずなので、お好みで拡張すれば良い。ただし、1525~30年あたりから統治技術が10に届き始める。ここまで順調に拡大できていればロシア化の最後の壁は統治技術10以上にすることとになっているため、最速でロシア化を目指すなら統治点が足りなくならない程度に拡張を抑えよう。植民地主義発祥の為のdevポチも必要だ。(植民地主義の受容をロシア化まで遅らせるのも良いかもしれない。)
また、同時並行で占領地の改宗も進める。宗教アイデア、ステート化、顧問の効果などをマシマシにすれば20カ月で改宗することが出来る。コーカサスの正教国家が滅びていれば正教国家は自国だけになるので信仰の擁護者にもなっておこう。

さて、ここで困ったことになった。なんとオスマンが同盟を切るというではないか。外交画面をのぞいてみるとよく見るとstavropol(マジャル)が欲しくて敵対的になってるらしい。1プロビ欲しいだけで関係性-95つくのは勘弁してもらいたいものだが、こういう時はそのプロビを売ってしまおう。早速クリミアにstavropolを売却したところ、即オスマンと同盟を結びなおすことができた。


オスマンと同盟を結びなおした直後、ヴァーシリー3世が逝去し、ヴァーシリー4世(2/3/5)が後を継いだ。オスマンとの緊張関係が続き、心労がたたったのだろう。彼の外交努力に敬意を表したい。
ロシアへの変態 1533年
大オルダを再度削った後の1533年に統治技術が10になったのでいよいよロシアに変態する。ロシア化することのメリットは様々だが、まずシベリア植民を行えることだろう。通常の植民と異なり、外交点を必要とする代わり、植民者を必要としない植民を行うことが出来る。ロシアは東方に広大なシベリアの未入植地があるのでこの能力を存分に生かすことが出来る。シベリアは開発度は1/1/1の不毛な土地だが、交易会社化すれば5ダカット程度の交易収入の他、工場を建てることで0.5ダカット程度の収入増は得られるため、将来的にみれば大きな収入源となる。何より、太平洋に到達する実績の達成には欠かせない能力だ。他にも、政府ランクが帝国に固定されるため、領土管理限界の制限が大分緩和されるので気楽に拡張することが出来るようになる。

また、ロシア化はなるべく早く行った方が良い。メリットが大きいことに加え、1600年までに東シベリアを領有する実績の条件は意外と時間の余裕はない。その為、シベリア植民の開始時期をなるべく早く行う必要があるのだ。本プレイは技術レベルを10にする際に-5%になるまで待ってしまったので、もう少し早く変態できるはずだ。
イギリス海峡への進出 1534年~
さて、いよいよコモンウェルスと対決しようと外交欄をチェックしていたところ、なんとコモンウェルスと同盟を組んでいる国にスコットランドがいるではないか。しかもスコットランドは最近まで組んでいたフランスとの同盟が何らかの要因で切れ、他に同盟国がいない据え膳状態である。これはコモンウェルスを叩く意味でも、イギリス海峡ノードに進出する意味でも見逃せない。ということでスコットランドに宣戦する。

コモンウェルス戦は砲兵を揃えた為占領合戦では優勢でワルシャワ陥落までいったが、戦闘に勝てず人的が切れそうだった為賠償金をもらい和平せざるを得なかった。コモンウェルスの軍質の高さを思い知らされた戦争だった。コモンウェルスとオーストリア(兼ハンガリー王)との同盟を切るか迷ったが、弱らせ過ぎてオスマンにハイエナされると不快なので賠償金を取って弱体化させ次回に拡張することにした。

また、リトアニアの種地を取りたかったがリトアニア文化のプロビが遠く断念した。よく属国解放の為のプロピ獲得でミスりやすい点だが、属国解放はプロビに中核州があってもそのプロビの文化が復活させようとしている属国の主要文化と同じでないと復活できない。イラクやバフマニーの解放でやりがちなので注意しよう。

コモンウェルスを叩くという目標は消化不良だったが、スコットランドを属国にしてブリテン島征服を視野に入れた所で今回は締めとさせていただきたい。次回からはいよいよコモンウェルスの解体と東方への進出を進めていくことになる。
前⇒モスクワAAR#1
次⇒まだ



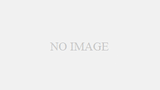
コメント